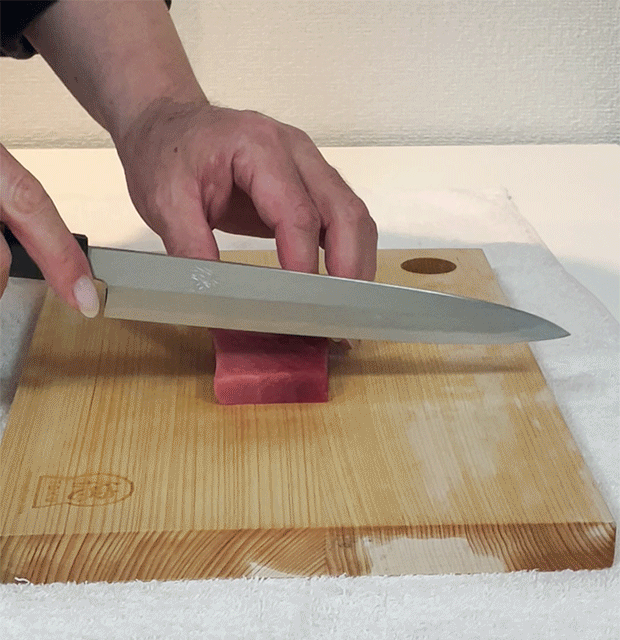
【2025年】包丁の使い方
「包丁の堺徳」のオーナー、奥平(おくだいら)です。
地元、大阪・堺の包丁を売りたいと思い堺の刃物メーカーから堺の包丁を仕入、販売しています。
単に包丁を売るだけでなく、お客様に包丁のことを理解してもらえるように、堺の鍛冶屋、刃付屋を何軒も訪問し、実際の作業を体験させていただき、職人さんからお話を伺ってきました。また、堺だけでなく、岐阜の関、新潟の燕三条、種子島、東京の葛飾の刃物製作所も訪問し、それぞれの特徴やこだわりなどの理解も深めるように努めています。
包丁の使い方
みなさんは包丁をどのように使用していますか?
また、どのようにすれば切れるか知っていますか?
『包丁の使い方なんてもちろん知ってるよ。普通に上から下に下ろせば切れるにきまってるじゃない。』
なんて思った方もいらっしゃるでしょう。
さて、それでは、その使い方、切り方は正しい使い方、切り方でしょうか?
『親か学校で習ったから、正しいんじゃないの?』と思った方いらっしゃいませんか?
でもよく考えてみてください。日本では小学校の家庭科の授業で包丁を使う機会があります。
そのとき、先生が教えてくれたことと言えば、左手の指を丸く内側にするということだけではなかったでしょうか?右手の包丁の動きについては、何も教わっていないと記憶しています。
包丁を使うときのイメージを思い浮かべてみてください。
昭和時代のドラマなどで朝、お母さんが台所で朝ごはんを用意しているシーンがあったと思いますが、包丁をまな板にコンコンコンコンと音を立てて切っているイメージないですか?
そのイメージから、包丁をまな板に向かって下ろすと切れるというふうに理解していないでしょうか?
また、コンコンコンコンと音を立てて切っていると、料理をしているというふうに見えます。
つまり、音を立てて切るというのは、撮影上の演出なのです。
実際にどんなに切れる包丁でも、包丁を上から下に下ろしただけでは何も切れないし、食材を押しつぶすことになってしまいます。
では、実際にはどのようにすれば綺麗に切れるのか?
それは、包丁を前後に動かすということです。包丁は前に押す、または、手前に引くことで食材を切ることができます。このことは普段、包丁をよく使っている方でも知らないことが多いです。
実際に、当店で実施している包丁研ぎ講習で包丁を研いだ後に試し切りをしてもらうのですが、新聞紙を上から下に下ろしてしまう方が多いです。そのようにしてももちろん新聞は切れません。
そこで、包丁を斜めにして手前に引くようにするとスパッと切れるのですが、なかなかできない方もいらっしゃいます。
ということは、包丁の使い方、切り方を教わってきたと思っていたけれど、実は正しい包丁の使い方、切り方は教わっていなかったということなのだと思います。もちろん、料理の専門学校に行かれた方は正しい包丁の使い方、切り方をご存じだとは思いますが。
切り方としては、押切りと引き切りがあります。
押切りは、包丁を前に押しだすようにする切り方、引き切りは刺身を切るときのように包丁を手前に引く切り方をイメージするといいでしょう。
包丁の持ち方は利き手で柄をしっかり握る持ち方と包丁の峰に人差し指を乗せたかたちの持ち方が基本です。
さて、ここまで読んでみて、ご自身の包丁の使い方、切り方はどうですか?正しく使えていたでしょうか?
もし、正しく使えてなかったという方はぜひ、この機会に改善されてみてはいかがでしょうか?
使い方、切り方が変わることで切れ味が変わり、味にも変化が出てくるのではないかと思います。
包丁の正しい使い方、切り方を覚えて、食を豊かにしましょう。
包丁販売店に行ってみよう!
包丁の堺徳は、東京・浅草に4月5日、店舗をオープンしました。東武浅草駅北口すぐのビルの6階にお店はあります。東京メトロ銀座線浅草駅からも徒歩3分ほどです。
研ぎ講習や研ぎ体験なども行っていますので、お近くにお越しの際はお気軽にお立ち寄りください。
包丁の堺徳では、YouTubeやFacebook、Instagramも展開しています。
ぜひ、チャンネル登録やフォローをお願いします。

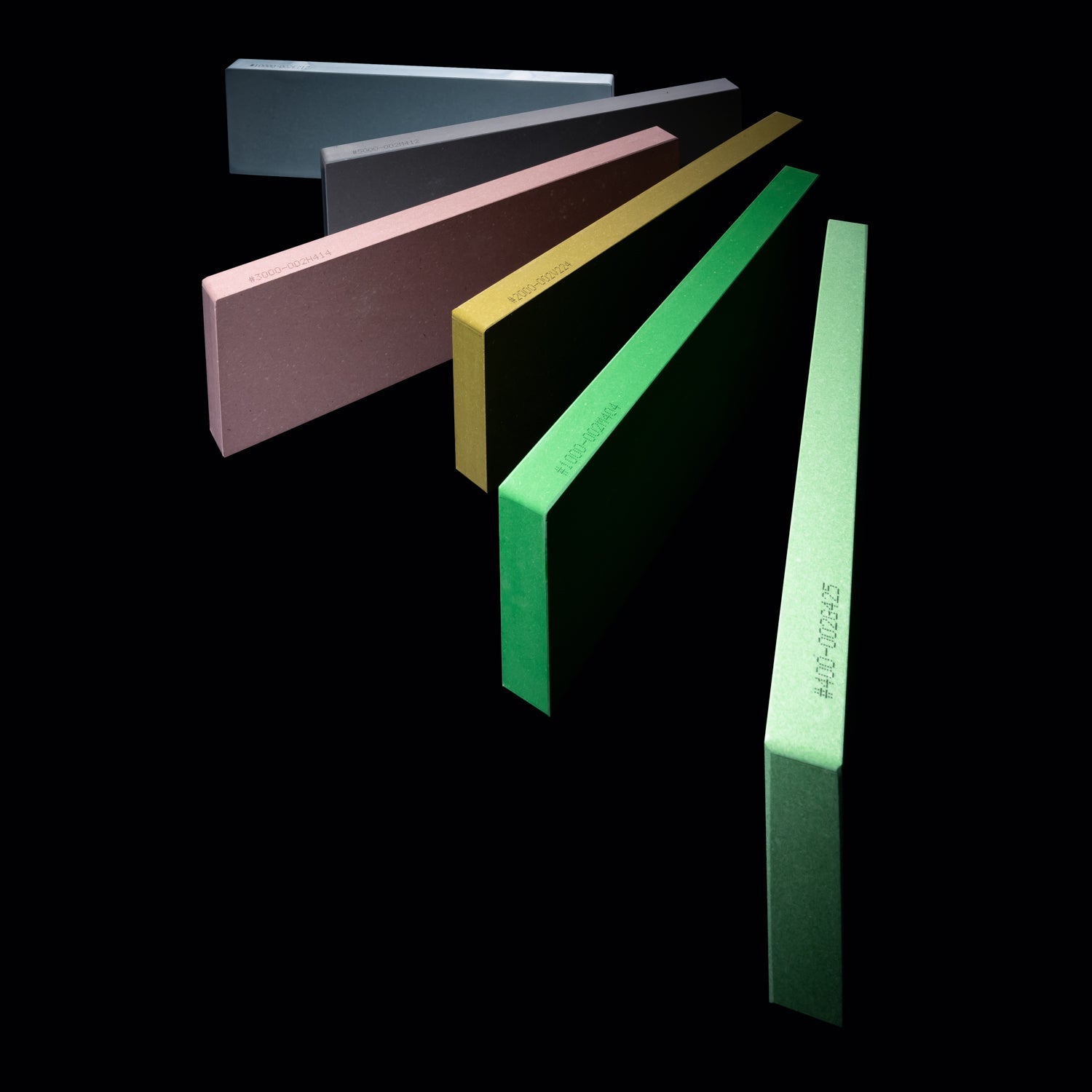

コメントを残す
このサイトはhCaptchaによって保護されており、hCaptchaプライバシーポリシーおよび利用規約が適用されます。